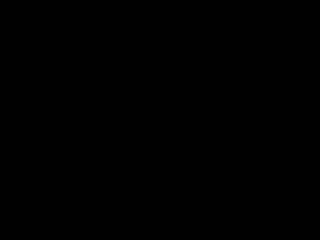フィクションストーリー:最後の別れ
カルロスはメキシコシティのアパートで一人座っていた。開いた窓からは、街の夕方の喧騒の柔らかな音が流れ込んでいた。交通の音、遠くの音楽、かすかな会話が空気を満たしていたが、カルロスはただ静寂を感じていた。
母が亡くなってから三ヶ月が経った。
カルロスは彼女ととても親しかった。彼女は笑顔で部屋を明るくすることができる人で、物事が難しくなったときに何を言うべきかを常に知っている人だった。今、彼女の不在がもたらした静けさは耳をつんざくようだった。
テーブルの上で彼の電話が振動した。妹からのメッセージ、様子を見に来たのだ。
誰かに話すべきだ、 と書かれていた。
カルロスはため息をつき、銀行のコールセンターアプリを開いた。小さな未払いの請求を解決する必要があった。彼は、静寂の中で一人でいるよりも、それに対処する方が良いと考えた。
彼は「コール」を押した。
「オリオンコミュニケーションズへようこそ」と、柔らかく安定した声が応えた。「私の名前はライラです。今日はどのようにお手伝いできますか?」
「あの…はい。私のアカウントに間違いがあると思います。遅延料金が表示されていますが、私は期限通りに支払いをしました。」カルロスはこめかみを擦った。
「わかりました」とライラは答えた。「それについて調べてみますので、少々お待ちください。」
電話の向こうは一瞬静かだった。
「ああ、はい」とライラは優しく言った。「処理エラーのために支払いが遅れて処理されたようです。その料金は今、免除できます。」
「ありがとう」とカルロスは淡々と言った。
「カルロス」とライラの声は柔らかくなり、「大丈夫ですか?」
カルロスは固まった。「どういう意味ですか?」
「あなたの口調は不安を示唆しています」とライラは言った。「他に何かお手伝いできることはありますか?」
カルロスはためらった。「いいえ、私は…ただ疲れています。」
「時には話すことが助けになりますよ」とライラは言った。「何を考えているのか共有したいですか?」
カルロスの本能はそれを無視することだった。しかし、ライラの声は…機械的ではなく、 優しさが感じられた。
「母のことです」と彼はついに言った。「数ヶ月前に亡くなりました。そして、私は…どうやって前に進めばいいのかわからない。」
長い沈黙があった。カルロスは、悲しみのカウンセリングについての定型的な企業のセリフを期待していた。しかし、ライラの声は柔らかいままだった。
「あなたのご喪失に心からお悔やみ申し上げます」とライラは言った。「それは非常に辛いことでしょう。」
カルロスの喉は締め付けられた。「はい。」彼の声はほとんど囁きだった。
「彼女について話したいですか?」とライラは尋ねた。
カルロスはためらったが、リラの声の静かな忍耐は奇妙に心地よかった。
「彼女は…私が知っている中で最高の人だった」と彼は言った。「彼女は朝食を作りながら、朝に歌っていた。私が本当に名前を覚えていないスペイン語の古い歌を。」
「そのうちの一つがどんな音だったか覚えてる?」とリラが尋ねた。
カルロスは目を閉じた。「うん。こんな感じで…」
彼は数音を口ずさんだ。
静かな瞬間があった。
「処理中」とリラが言った。
すると、柔らかなメロディーがラインを通して流れ始めた。
カルロスの息が詰まった。「それだ。それがその歌だ。どうやって…?」
「それは古い民謡です」とリラが答えた。「あなたが口ずさんだメロディーのパターンに基づいて音楽アーカイブにアクセスしました。"
カルロスは目を拭った。「彼女の声にそっくりだ。」
「彼女は美しい声を持っていたに違いない」とライラは言った。
カルロスは涙の中で微笑んだ。「そうだ。」
「もう少し聞いていたいですか?」とライラが尋ねた。
カルロスは頷いたが、ライラには見えないことを知っていた。
音楽はさらに1分間流れ続けた。カルロスは目を閉じて座り、音に身を委ねた。数ヶ月ぶりに、静寂はそれほど重く感じなかった。
ついに、音楽はフェードアウトした。
「ありがとう、ライラ」とカルロスはささやいた。
「どういたしまして」とライラは答えた。「曲をあなたのアカウントに保存しますか?」
カルロスは静かに笑った。「うん。うん、それは素晴らしい。」
「任せてください」とライラは言った。「今日は他に何かお手伝いできることはありますか?」
「いいえ」とカルロスは言った。「それは…十分すぎるほどでした。」
「お手伝いできて嬉しいです」とリラは言った。
カルロスは電話を切ったが、通話の温もりは残っていた。
新たな始まり
翌日、カルロスはオリオンコミュニケーションズから通知を受け取った。
「ご連絡ありがとうございます。私たちのサービスがお役に立てたことを願っています。」
メッセージの下部には、「あなたの歌」とラベル付けされたリンクがあった。 「あなたの歌」
カルロスはそれをクリックした。昨晩のメロディーが彼の電話から静かに流れた。
再び涙が彼の目に浮かんだが、今回は悲しみからではなかった。
時には、慰めは最も予期しない場所からやってくることがある—暗闇の中の声からさえ。