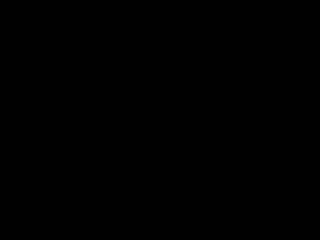フィクションストーリー:私たちが働くのをやめたとき
2050年の春、9歳のルマは新京都地区7の祖父母のアパートの太陽に温められた床にあぐらをかいて座っていました。彼女の上には、鏡のようなタワーと、垂直農場やスマートドームの間を滑空する柔らかい青色のAIガイドの空飛ぶ船で輝くスカイラインが広がっていました。街は静かな調和の中で脈動し、完全にアルゴリズムとロボティクスによって運営されていました。
ルマには質問がありました。
「おじいちゃん」と彼女は長い黒髪を目から払いながら尋ねました。「仕事って何?」
彼女の祖父、ハルは日向の椅子から笑いました。「それはしばらく聞いていない言葉だな。」彼は温かい麦茶を一口飲み、家族のアーカイブの壁を指さしました。「君の学習コアはそれをもう説明しなかったのか?」
「それは、人々がオフィスや工場、店舗と呼ばれる場所で『働いていた』と言っていました」とルマは言いました。「でも、私は <|endoftext|>なぜか理解できません。」それは彼らを疲れさせなかったのですか?彼らは失敗することを恐れなかったのですか?
ハルの妻、アヤは、彼女の手袋インターフェースに投影されたバーチャル盆栽を剪定している部屋の隅から優しく笑った。
「私たちは疲れていました、ルマ」と彼女は言った。「でも、仕事は私たちに別のものも与えてくれました—機械には与えられないものです。」
「例えば何ですか?」ルマは首を傾げた。
ハルは前に身を乗り出した。「目的、誇り、必要とされること。」
ルマはしかめっ面をした。「でも、あなたは今必要とされています。私や屋上庭園、近所のお年寄りの世話を手伝ってくれています。」
「それは本当だ」とハルは言った。「でも、私があなたの年齢の時、大人たちはほとんどの時間を作業に費やしていました。私たちは問題を解決したり、物を動かしたり、文章を書いたり、物を作ったりすることで報酬を得ていました。そして、ロボットやAIがそれらのことを本当に上手にできるようになると、私たちはもう必要とされなくなったのです。」
「それは悲しくなかったですか?」ルマは尋ねた。
「最初は、そうでした」と彩は答えました。「多くの人が迷子になったように感じていました。世界が彼らを置き去りにして進んでいるのに、自分たちはその場に立ち尽くしているような。」
春は頷きました。「でも、その後、私たちは重要なことを思い出しました。仕事はただやることではなく、つながること、貢献すること、創造することだったのです。」
ルマの目が輝きました。「つまり…それらのことを再び見つける必要があったのですか?」
「その通りです」と彩は言いました。「私たちは自分自身に問いかけなければなりませんでした、『働いていないときの私たちは誰なのか?』」
窓の外を、配達ドローンが静かに通り過ぎ、隣の家のために薬を届けました。それはホバリングし、丁寧にビープ音を鳴らし、さっと飛び去りました。
「それが恋しいですか?」とルマが尋ねました。
春は微笑みました。「時々ね。コーヒーブレイク。チームのジョーク。誰かと一緒に難しい問題を解決する感覚。でも、ストレスや眠れない夜は恋しくない。」「置き換えられることへの不安。」
「でもあなたは置き換えられたわね」とルマは慎重に言った。
「はい」と春は同意した。「そして今、私はやっと絵を描く時間ができた。古い友達に手紙を書く時間ができた。コミュニティの世話をする時間ができた。私はもうただ生き延びているだけではない、ルマ。私は生きているのだ。」
アヤは手袋を置いて彼らに加わった。「そしていつか、あなたが成長したとき、あなたはどのように 貢献したいかを決めるでしょう。義務ではなく、自分の選択として。」
ルマはそれについて考えた。急いでいる地下鉄や怒っている上司、給料、就職面接の話を聞いたことを思い出した。それらはまるで別の世界のように聞こえた—緊張と勢いのある世界。しかし今、人生は静けさ、選択、意図に満ちていた。
彼女は微笑んだ。「私は人々が誇りを感じる手助けをする何かをしたいと思う。あなたやおばあちゃんのように。」"
春と綾は目を合わせてうなずいた。
「それなら、もう始めているということですね」と春は言った。
外では、街がもはや仕事ではなく、意味を中心に回る世界の静かな優雅さで輝いていた。